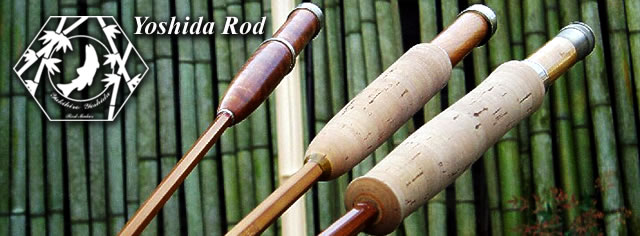
当ロッドの工程の特徴的な部分を、一部公開できるものについて掲載してみました。

1wtライン用から11wtラインまでフルカスタムメイドにつき、長さ1インチ刻み、番手やアクション、外観部分まで細やかなご指定が可能です。内容によってはオプション料金が発生する場合もございますので、ご確認ください。

11月に入り一霜降りると竹取シーズンの始まりです。大体、年内いっぱいで切り終えます。
晩秋になると竹内部の水分量が減り、身も締まるので乾燥中の狂いも抑えられる上、虫やカビも付きにくいです。
都合が許す限り、新月の1週間前から当日までの間に切るようにしています。古くから竹にかかわる人達の間で言われていることですが、西洋でもバイオリン用の木材や、建築材料でも同じことが言われているのは興味深いです。
竹の状態にもよるので一概には言えませんが、使うのは根元節間30cm位になるあたりから、枝の直下までで、2m前後で4本ほど取ります。
あとは、繊維の充実度、硬さ、粘り、重さ、節間等より判断して、各モデルに振り分けて使います。
伐採後、出来るだけ早めに割りに入ります。半乾きだと非常に割りにくいし、あまり長期間放って置くと内部から腐敗し始めるのが理由です。大小の竹割りナタとゴム槌を使い8等分した後、紐で縛って保管します。
この段階でいろいろな情報を竹から貰うことの出来る楽しい作業ですが、100本ほど切ると割るのに1−2ヶ月掛かる重労働となります。
伐採後最低3年、現在は在庫の状況により5年以上乾燥させた物を使っています。
木材では「乾燥開始後3年以降、セルロースの硬化が・・・(以下略)」という資料もありましたが、私は学者ではないので、詳しいことは良くわかりません。
作業上の感覚的なことで言うと、長期乾燥させたもののほうが、火入れがし易いということは確かだと思います。
伐採直後の割りのあと、すぐに室内乾燥します。出来るだけゆっくり乾かしたほうが矯め傷も付き難いことから、硬い素材を得られるようです。
ナタで分割しつつ、節部の繊維の状況、曲がり、硬さ、粘り具合などを元に「使いたい」と思うピースを選んでいきます。素材1セクションから大体ロッド1〜2セクション分、よほど素性の良いものでもう1セクション余分に取れる程度です。
残りは一部を修理用を含む予備材に、あとは炭火を起こす際の種火に使い、それ以外の残りは肥料として藪にお帰り頂いています。
炭火で曲がっている箇所だけでなく、ピース全体に出来るだけ均一に火が入るように炙っていきます。
初回は強い、硬めの火で大まかに伸ばし。その後、数日寝かした後に細部まで矯正、ほぼ定規面がでたら、あとは様子を見つつ火を入れ、素材にこの状態を記憶させます。
荒削りで寸法を追いつつ、その間に数回(回数は内緒)炭火で火を入れます。
それぞれのインターバルは1日〜1週間程度、目的、天候等により期間は変動します。